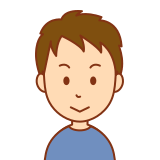
(1)HSPだと休むことに罪悪感をもつのはなぜ?
(2)休むことに罪悪感を持ったら、どうしたらいい。
(3)罪悪感を放置すると、どうなるの?
この疑問に答えます。
実はHSPが休むことへの罪悪感の原因は、幼少期に両親(養育者)から受け取ったある感情がきっかけです。
HSPはこのメカニズムを認識するだけで、生きづらさが軽減します。
- HSPの休むことへの罪悪感は
幼少期の刷り込みから - 休むことも仕事だと考えれば
罪悪感が少ない - 休む罪悪感を放置すると
「隠れうつ」に
HSPは感受性と内向性が強くあらわれた人です。
内向性は「成功してはいけない」という禁止事項を自分に課しています。
「成功してはいけない」の感情にふれるとどうなるか。
HSPは「自分が強くなくては」という衝動に駆られます。
休むことは自分が弱いことを周囲にアピールしてしまうこと。
休んではダメだ、と自分に強さを求め、休むことをためらう衝動に駆られます。
感受性は「怒ってはいけない」という禁止事項を自分に課しています。
「怒ってはいけない」の感情にふれるとどうなるか。
HSPは「相手を喜ばせなくては」という衝動に駆られます。
相手も忙しいのに、自分だけ休むことは相手を怒らせてしまうかもしれない。
休んではダメだ、と相手を喜ばせようと、休むことをためらう衝動に駆られます。
これが、HSPが休むことへ罪悪感をもつ理由です。
結論、休むことへの罪悪感は幼少期に自分に刷り込んだ思い込みがきっかけ。休むことに罪悪感をもつのではなく、許可してください。
本記事を読むことで、HSPが休むことへの罪悪感をもつメカニズムがわかります。
私は内向型HSPの当事者として、40年以上すごしてきました。
そして、交流分析という心理理論を学び、
HSPについて生きづらさを軽減するための情報を発信しています。
幼少期に自分に刷り込んだある感情が、HSPの性格を形成し
生きづらさを生み出していることを知りました。
交流分析では人の性格を人生脚本で表現します。
HSPは6つある脚本のうち、2つを多用します。
この2つの脚本を多用するため、
HSPは休むことへの罪悪感をもつ場面が多くなります。
HSPがなぜ休むことに罪悪感を持つのか

HSPはストレスが強くかかると「自分はOKでない」構えになるからです。
要するに、自分を責めるメカニズムがあります。
これが休むことへの罪悪感につながります。
HSPが罪悪感をもつときに、交流分析では次の衝動に駆られることが知られています。
- 自分が強くなければいけない
- 相手を喜ばせなければいけない
この二つの衝動は、幼少期に親(養育者)から味わった「ある感情」がきっかけと言われています。
その感情とは
- 成功してはいけない
- 怒ってはいけない
です。詳しくはあとで説明します。
例えば、「自分が強くなければいけない」は自分が休みたい感情をおもてに出すのは目立ってしまうため、我慢しようとします。
「相手を喜ばせなければいけない」は自分が休むことで、誰かに迷惑がかかってしまわないか気になるため、我慢しようとします。
繁忙期の会社で自分が休むことを誰かに伝える、自分だけ休むことが後ろめたい気分になるのは、この2つの衝動が理由です。
「自分が強くなければいけない」
→「(自分が)強くあれ」
「相手を喜ばせなければいけない」
→「相手を喜ばせよ」と表記します。
「(自分が)強くあれ」、「相手を喜ばせよ」の衝動が強くあらわれると、
HSPは休むことに罪悪感をもちます。
- 幼少期に味わったある感情がきっかけ
- 「(自分が)強くあれ」
の衝動が強くあらわれるから - 「相手を喜ばせよ」
の衝動が強くあらわれるから - 「私はOKでない」
→自分を責める傾向が罪悪感に
親から受け取ったある感情が起源
HSPが罪悪感をもつのは、幼少期に親(養育者)から味わった「ある感情」がきっかけと言いました。
その感情とは
- 成功してはいけない
- 怒ってはいけない
です。
根拠は交流分析という心理理論からアプローチしています。
交流分析について簡単に説明しますと、1950年代後半に、
精神科医エリック・バーンによって提唱された理論です。
彼は「人間はゆりかごから墓場まで、人生脚本を演じ続ける」と主張しています。
自分自身の人間関係や認知傾向を知り、対人関係の問題を解消したり、
トラブルを回避したりするための心理療法になります。
HSPの生きづらさは、すでにエリック・バーンによって浮彫りになっていたんです。
内向性と感受性に分けて考える
HSPになるのは、あなたが3歳までに両親から受け取ったある感情が原因といわれています。
大人になってもその感情を味わうことをしないよう、人生脚本を忠実に演じつづけます。
これに気づかないと生きづらさは死ぬまで続くことになります。
人生脚本は6種類あります。
HSPは自分を責めやすい、2つの脚本を多用しています。
自分を責めやすい理由に関しては、こちらを参考にしてください。
話を戻します。
HSPは2つの人生脚本を多用すると言いました。
どんな脚本なのかというと、内向性と感受性です。
HSPが休むことに罪悪感をもつ理由は、感受性と内向性に分解するとシンプルになります。
HSPの人生脚本
| 人生脚本 | HSPとの関係性 |
| A | なし |
| B | なし |
| C | なし |
| D | 感受性 |
| E | 内向性 |
| F | HSS |
人生脚本は禁止令、拮抗禁止令、プログラムという構成になっています。
| 人生脚本の構成 | 説明 |
| 禁止令 | 「〇〇してはいけない」 ブレーキの役割。 |
| 拮抗禁止令 | 「〇〇しなくてはならない」 アクセルの役割。 |
| プログラム | いまココに対処する 実際の行動 |
禁止令「〇〇してはいけない」に違反しそうになると、
拮抗禁止令「〇〇しなくてはならない」という衝動に駆られます。
例えば、前を走っているクルマがブレーキだけで避けられなかったら、アクセルを踏むしかないですよね。そうやって事態に対処していると考えてください。
禁止令、拮抗禁止令が台本だとすると、プログラムは俳優(あなた)に相当します。
つまりは禁止令、拮抗禁止令は台本に書かれているだけで、台本通り演じなくてもいいことになります。
台本通り演じると不都合(生きづらさ)が生じることもあります、アドリブもしていいんです
(内向性)「自分が強くあれ」
HSPはなぜ、「成功してはいけない」のか。
あなたが幼少期に「成功してはいけない」感情を味わう経験をしたからです。
例えば、あなたが幼少期に成功体験を両親にアピールしたとします。
ハイハイをして成功したことを両親にアピールした、または”おむつ”を替えて欲しくて泣いてアピールしたとします。
ところが、両親はそれに関心を示さない。
またはなかなか面倒を見てくれなかった。
などの経験をすると、自分は成功をしてはいけないんだという感情を味わいます。
成功をアピールしたけど、相手にしてもらえなかった、
もしくは成功を否定する言葉や態度で対応された。
あくまで一例です。
いや両親はちゃんと面倒見ていたよという意見もあるかもしれません。覚えていないだけです。
成功をアピールしたけど期待するリアクションが得られず、
「成功してはいけない」感情として受け取ったのです。
すると、成功することを避けるよう禁止するルールを自分の人生脚本に刻み込むのです。
「自分が本当に手に入れたいものを、手放してしまいます。」
| 内向性の人生脚本 | 内容 |
| 禁止令(メイン) | 「成功してはいけない」 |
| 禁止令(サブ) | 「目立ってはいけない」 |
| その他にもある | |
| 拮抗禁止令 | 「自分が強くなくてはならない」 |
| プログラム | (本心は一人の時間、 空間を過ごしたい) |
内向性の人生脚本のシナリオはこうです。
禁止令「成功(アピール)してはいけない」
禁止令に抵触しない限り、
プログラム「誰とも関わらず一人で過ごしたい」
とはいえ、成功するためにみんな会社に行っているし、成功するためには会社で誰かと顔をあわせなければならない。禁止令に抵触しそう・・・。そんなときは
拮抗禁止令「自分が強くなくてはならない」が作用します。
自分だけ休むことは成功(アピール)につながる、
ひょっとしたら休むことで相手の気分を害するかもしれない。
休むことは自分が強くないことだ、自分が強くあるためには、休まず我慢しよう。
どうしよう。(←いまココ)
でも、想像してみてください。脚本には禁止令、拮抗禁止令が書いてありました。
これって守る必要ありますか。ただの思い込みですよね。こんな縛りプレーしていたら、生きづらくないですか。
(感受性) 「相手を喜ばせよ」
HSPはなぜ、「怒ってはいけない」のか。
あなたが幼少期に「怒ってはいけない」感情を味わう経験をしたからです。
例えば、あなたが幼少期に両親から怒りを感じる場面に遭遇したとします。
①兄弟(姉妹)が自分の持っているおもちゃを横取りされ怒りを両親にアピールした、または②両親が”夫婦喧嘩”を自分の目の前で始めたとします。
ところが、①両親は怒りを抑えつける言葉、態度を自分に示した。
または②夫婦喧嘩はヒートアップして、命の危険を感じるほどの怒りを体験した。
あくまで一例です。
その結果、①怒りをアピールしたけど期待するリアクションが得られなかった、
②命の危険を感じるほどの怒りを体験した。
これらを「怒ってはいけない」感情として受け取ったのです。
すると、怒りを避けるよう禁止するルールを自分の人生脚本に刻み込むのです。
感受性の人生脚本は禁止令「怒ってはいけない」がメインにあります。
| 感受性の人生脚本 | 内容 |
| 禁止令(メイン) | 「怒ってはいけない」 |
| 禁止令(サブ) | 今回は割愛。 |
| その他にもある | |
| 拮抗禁止令 | 「相手を喜ばせなくてはならない」 |
| プログラム | (本心は人として受け容れられたい、 感覚的な心地よさを得たい) |
感受性の人生脚本のシナリオはこうです。
禁止令「怒ってはいけない」
禁止令に抵触しない限り、
プログラム「人から好かれたい、気に入られたい、リラックスする時間が欲しい」
とはいえ、実生活で理不尽な場面に怒りを覚えることもあります。
禁止令に抵触しそう・・・。そんなときは
拮抗禁止令「相手を喜ばせなくてはいけない」が作用します。
休むことは、相手に迷惑をかけ、怒りの感情を持たせるかもしれない。
なるべく、怒りにふれることは避けたい。
そうだ、休まないほうが相手を喜ばせることになるだろう。もし休んだら、相手を喜ばせることにならないのでは。休むことに、罪悪感がある。どうしよう。(←いまココ)
でも、想像してみてください。脚本には禁止令、拮抗禁止令が書いてありました。
これって守る必要ありますか。ただの思い込みですよね。こんな縛りプレーしていたら、生きづらくないですか。
HSPの罪悪感は非HSPに比べ表面化しやすい
ところで、HSPがもつ2つの衝動「自分が強くあれ」、「相手を喜ばせよ」がなぜ罪悪感につながるの?と疑問に思うかもしれません。この2つの衝動に駆られている間、HSPは「私はOKでない」という構えになるからです。この構えのことを、交流分析では人生態度と呼んでいます。
例えば、「自分が強くあれ」は言葉のとおりで、休むことは弱いやつがすることだ、自分は強くなければいけないから休むことはあり得ない。
「相手を喜ばせよ」は、自分が休んだことで誰かが困るのではないか、誰かの怒りに触れるのではないか。そうであれば、相手を喜ばせるために、休むことはできない。
自分はOKでないから、相手からOKと言われるためには休んではいけない。つまり自分を責めている状態に近いです。これがHSPの罪悪感として表れます。
HSPの罪悪感は非HSPに比べると、表面化しやすいです。
| 人生脚本 | 構え(人生態度) |
| A 非HSP | 「私はOK あなたはOKでない」 |
| B 非HSP | 「私はOK あなたはOKでない」 |
| C(感受性) HSP | 「私はOKでない あなたはOK」 |
| D(内向性) HSP | 「私はOKでない あなたはOK」 |
| E(HSS) | 「私はOK あなたはOKでない」 |
| F 非HSP | 「私はOK あなたはOKでない」 |
- 幼少期に味わったある感情がきっかけ
- 「(自分が)強くあれ」
の衝動が強くあらわれるから - 「相手を喜ばせよ」
の衝動が強くあらわれるから - 「私はOKでない」
→自分を責める傾向が罪悪感に
このように感受性と内向性の両方の心の仕組みがあるため、
HSPが休むことに罪悪感をもつのです。
HSPが休むことに罪悪感をもつ場面への対策

休むことに対して、自分で自分に許可してください。
休んだ方が仕事の生産性があがるからです。
会社は利益つまり、生産性を向上するための組織です。
この目的と休むことは一致しているので、休むことも仕事と考えれば自分を正当化することができます。
仕事のうちだと考えてみるのはどうでしょうか。
HSPが休むことへ許可する方法は以下のとおりです。
- (内向性)「自分が強くあれ」
自分が強くなくていいと許可する - (感受性)「相手を喜ばせよ」
まずは自分を喜ばせる
最初は自分に許可するのは難しいかもしれません。例えば、利き手を右から左に変えるような感覚に近いです。許可できたら、自分で自分をほめることを忘れないでください。次第に休むことに対して、罪悪感はうすれていくでしょう。
休んだことで生産性があがっている、会社に貢献していると考えてください。
とはいえ、最初は罪悪感をなくすことは難しいかもしれません。
自分に許可がうまくできない場合は、以下の対策でしのいでください。
- 誰かの休みに便乗する
- 休みをあらかじめ決めてしまう
- 休みの電話代行サービスの活用
①誰かの休みに便乗する
誰かが休んだタイミングで、自分も一緒に休む連絡をするのはどうでしょうか。
誰かが休んだのだから自分も休む、と言い出しやすいからです。
例えば、いまはLINEやチャットツール(slack)などで勤怠管理している会社がほとんどです。誰かが「休みます」とメッセージがきたら、そこに便乗して自分も休むと申し出てしまいましょう。
いや、うちの会社は休みの連絡は電話連絡しか受け付けていません。 という意見もあるかもしれません。その場合は次の対策に進みます。
メリット:自分から言い出す罪悪感が減る
デメリット:誰かが休まないと休めない②休みをあらかじめ決めてしまう
有給が付与された段階で、あらかじめ「この日とこの日」休みますと宣言してしまいましょう。
何回も小出しに休むと、罪悪感の頻度が高くなります。最初から休みを宣言しておけば、現場が多少いそがしくても休みやすいです。
忙しいのはあなたの責任ではなく、会社の責任になるからです。
そうすると、上司から出勤してくれないかという場面が想定できます。しかし、絶対に断ってください。
メリット:罪悪感をもつ頻度を減らせる
デメリット:休みを決めすぎると
緊急時に休めなくなる③休みの電話代行サービスの活用
どうしても、休むこと「自分の本心を打ち明ける」が怖い場合は、電話代行サービスもあります。月曜日に会社に行きたくない場合で、休みを延長する場面になどで活用できそうです。

メリット:緊急で対応してくれる
デメリット:1万円と高い休む罪悪感を放置すると「うつ」に

休むことへの罪悪感を放置すると、「隠れうつ」になります。
私が実際に経験したことがあるからです。
当時システムエンジニアとして、会社に勤めていたときの話です。
そこは10名ほどの部署で、毎日だれか一人は休むような環境でした。
ところが、だれかが休むのにはちゃんとした理由があったんです。
なぜなら、その会社は2か月に1人退職するブラック企業だったからです。
私の中のHSPの衝動「(自分が)強くあれ」、「相手を喜ばせよ」が強く作用してしまったのです。
当時の心境はこんな感じ。
「(自分が)強くあれ」
→何回も当日になって休むなんて、
社会人失格だ。出社しなければ。
「相手を喜ばせよ」
→休んだ人の仕事も誰かがやらないと困る。
自分が引き受けよう。休むことを怠った結果、医者からは「”うつ”です。」との診断が下りました。
気づいたら、「うつ」になっていたんです。
通常、
出社できなくなる→病院→「うつ」
の流れだと思います。
私の場合、
出社している状態→病院→「うつ」
の流れでした。
そうとう我慢していたのが、伝わったかと思います。
「うつ」になるとどうなるかというと、いいことが1つもありません。
- 何もできなくなる
- 好きなことが楽しくない
- 時間だけがただ流れる
- 再発リスクが高い
HSPは休む罪悪感を放置すると危険です。
みなさんにこうなって欲しくないので、
HSPは普段からどのように休んだらいいのか、
HSPの限界のサインをまとめました。
よかったら、ご覧ください。
まとめ
本記事のまとめです。
- 幼少期に味わったある感情がきっかけ
- 「(自分が)強くあれ」
の衝動が強くあらわれるから - 「相手を喜ばせよ」
の衝動が強くあらわれるから - 「私はOKでない」
→自分を責める傾向が罪悪感に
- (内向性)「自分が強くあれ」
自分が強くなくていいと許可する - (感受性)「相手を喜ばせよ」
まずは自分を喜ばせる
休むことへの罪悪感に慣れるまでの対策
- 誰かの休みに便乗する
- 休みをあらかじめ決めてしまう
- 休みの電話代行サービスの活用
今回の話のつづき、特にHSPと非HSPの違いをもっと詳しく知りたいかたは、こちらをご覧ください。KindleUnlimited(読み放題サービス)なら無料で読むことができます。




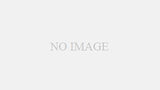
コメント